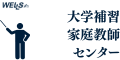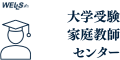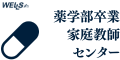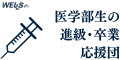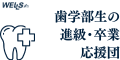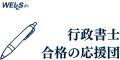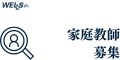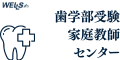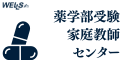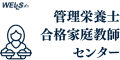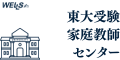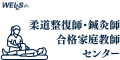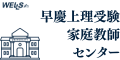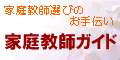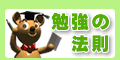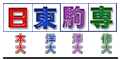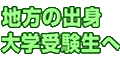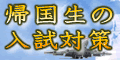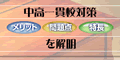2浪のメカニズムを止める:月別リスクとやさしい対策
はじめに
春に始まった受験の1年は、気持ちも環境も少しずつ変わっていきます。
「やる気が続かない」「授業に戻りにくい」「模試を後回しにしてしまう」——どれも、あなたの力不足ではなく、季節や生活のリズムの影響を受けやすいだけ。ここでは4月〜12月の流れに沿って、無理のない対処をまとめました。
全体像(4〜12月の“よくある流れ”)
- 4月:新しい環境に慣れるので精一杯。
- 5月:疲れがたまりやすく、手が止まりがち。
- 6〜8月:暑さや長日でペースが乱れやすい。
- 9〜10月:遅れの自覚が焦りに変わり、手数が散らばる。
- 11〜12月:日が短く、1日が短く感じるため、開始が遅れやすい(日の出入・日照の実測は、公的サイトでいつでも確かめられます:※こよみの計算/※過去の気象データ)。
月別リスク → やさしい対策
4月:新スタートの反動
- 起きがち:新しい教材やルーティンが増えて、手が散らばる。
- そっと対策:やることを「固定3本」に絞ります(例:英長文15分/数計算15分/古文10分)。「短く始める」からで大丈夫。
5月:“中だるみ”の入口
- 起きがち:「頑張れていない自分」を責めて止まる。
- そっと対策:1日の最初に一番短いタスク(5〜10分)を置き、始めたらOKにします。慣れたら少し延ばしましょう。
6〜7月:暑さ・長日で乱れやすい
- 起きがち:寝つきが悪くなり、朝が遅れ、夜型へ。
- そっと対策:就寝・起床の時刻だけ固定。どうしても夜型なら、朝は“短時間の外光”で体内時計を戻しやすくします(気象庁の日照データや季節の天候ページが参考になります:※日本の季節の天候)。
8月:学習ペースの“空白”
- 起きがち:学習時間よりスマホ滞在が増える。
- そっと対策:復帰の最初はタイムトライアル(15/30/60分)×1本だけでも良いです。
端末の保有・利用傾向は総務省の公的調査にもまとまっています(家庭の機器保有や個人の端末利用状況:※通信利用動向調査)。ご家庭でルールを決める材料にどうぞ
9月:授業復帰の“よそ者感”
- 起きがち:授業に戻るのが怖く、「分からないかも」で足が止まる。
- そっと対策:復帰1週目は出席+メモのみでOK。「分からない」を集める週、と決めます。
※集めた「分からない」は3件だけ、次週に先生へ相談。
10月:焦りで“手を広げすぎる”
- 起きがち:「まだ半年ある」と思ったまま、教材を増やす。
- そっと対策:固定日(出願・本試験)から逆算し、1校の過去問“縦解き”へ集中。固定日は大学入試センターの公式で確認できます(※受験案内/※実施要項)。
11月:日が短く“開始が遅れる”
- 起きがち:夕方から焦って量を増やし、質が落ちる。
- そっと対策:開始時刻を1つ決めて固定。朝の外光を1〜3分浴び、短時間×回数で積み上げ。
日照や日出・日没は、国立天文台の暦計算や気象庁の平年値で“短く感じやすい”背景を確認できます(※こよみの計算/※平年値(日ごとの値))。
12月:情報過多で空回り
- 起きがち:SNSやまとめ情報を見過ぎて、不安が増える。
- そっと対策:同一大学の過去問“縦解き”+時間短縮の確認にやさしく絞ります。
相談先やメンタルの寄りどころは、公的調査の「困ったときの相談」項目も参考に(こども家庭庁の調査まとめ:※こども・若者の意識と生活)。
合格に向けた“ぶれない土台”
- 固定日(出願・本試験)を最優先でカレンダー化。
- 縦解き→再現答案→時間短縮の順に、同じ大学で深く。
- 就寝・起床の固定と朝の光で、体内時計をやさしく整える。
- 端末ルールは家族合意で。保有・利用状況は公的統計を根拠に(※通信利用動向調査)。
参考(※参照名|日本の公的情報のみ)
- 国立天文台|※こよみの計算(日の出・日の入り、季節の明暗)
- 気象庁|※過去の気象データ/※日本の季節の天候(日照・季節の推移)
- 総務省(e-Stat)|※通信利用動向調査(世帯・個人の機器保有・利用状況)
- 大学入試センター|※受験案内/※実施要項(出願〜本試験の“動かない日付”)
- 文部科学省・e-Stat|※学校基本調査(令和6年度)結果の概要(統計用語・年次概況)
- こども家庭庁|※こども・若者の意識と生活(困った時の相談・普段の活動)
無理をしなくて大丈夫です。
まずは「固定日を確認」「開始時刻をひとつ決める」の2つから。季節に合わせて、少しずつ歩幅を整えていきましょう。