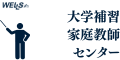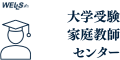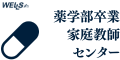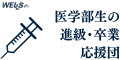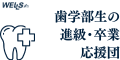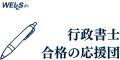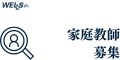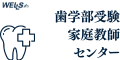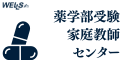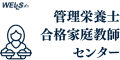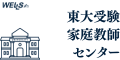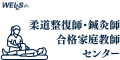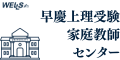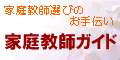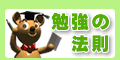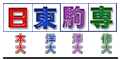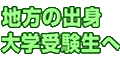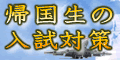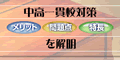志望校と併願の選び方—浪人生が“落ちにくい出願”を作るためのいちばん簡単な方法—
■はじめに
「この志望校で大丈夫かな…」
「併願をどう組めば全部落ちずに済むんだろう…」
浪人生の多くが悩むのが、この“出願の決め方”。
でも実は、見るべきポイントは
①配点 ②方式 ③共通テスト比率
この3つだけで十分です。
そして併願は、
安心2:実力2:挑戦1
にするだけで崩れにくくなります。
さらに大事なのは、
やりたいことが明確でなくても志望校は決められる ということ。
1)まずは“今年の公式情報”に戻る
浪人生が一番やりがちな失敗は、
前年の情報やSNSの噂をそのまま信じること。
入試は毎年、どこかが必ず変わります。
だから、最初に見るのはこの3つの“公式情報”です。
●共通テストの科目・配点・手続き
→ 大学入試センター「受験案内」
https://www.dnc.ac.jp/sp/kyotsu/shiken_jouhou/r6_gaiyou.html
●出願〜試験の流れ
→ 大学入試センター「実施要項」
https://www.dnc.ac.jp/sp/kyotsu/shiken_jouhou/r6_jisshi.html
●大学の選抜の考え方(方式の大枠)
→ 文部科学省「入学者選抜実施要項」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/nyushi/1412172.htm
これらは「誰がどう決めているのか」を示す公式資料。
迷ったらここに戻れば、情報迷子になりません。
2)“相性の良い大学”は、この3つを見ると一発でわかる
浪人生は1年勉強したことで、
- 伸びた科目
- 安定してきた科目
がはっきりします。
大学側も
「この科目ができる受験生に来てほしい」
というメッセージを、配点や方式で示しています。
だからこの3つを見るだけで、
“今年の自分と相性のいい大学”=“受かりやすい大学”
が自然に絞れます。
●① 配点
伸びた科目の配点が重い大学は戦いやすい。
例:
- 英語Rが伸びた → R重視の大学
- 国語の記述が得意 → 記述中心の大学
- 数Ⅲが厳しい → 数Ⅲ比重の大きい大学は消耗が大きい
●② 方式(記述/マーク)
- 記述力が伸びた浪人生 → 記述多めの大学
- マークの正確さが上がった浪人生 → マーク比重の大学
方式だけでも相性は大きく変わります。
●③ 共通テスト比率
浪人生は共通テストが 安定しやすい。
だから比率が高い大学は合格可能性が読みやすく、相性が良い。
3)併願は「安心2・実力2・挑戦1」で崩れない
浪人生が落ちやすくなる併願の例:
- 挑戦校ばかり受ける
- 去年の悔しさで“上”に寄せすぎる
- 安全校を「受けたくない」で外す
これは全落ちリスクが一気に跳ね上がるパターンです。
✔ だから、こう組めば安定する
- 安心(確実なライン)……2校
- 実力(本命)………………2校
- 挑戦(やや上)……………1校
このバランスが最も崩れにくく、点数が安定します。
4)「行きたい大学」が決まらないときの考え方
浪人生によくある悩み:
「やりたいことがまだハッキリしない」
「志望理由が思いつかない」
実はこれ、普通です。
●エビデンス:興味は18〜22歳で大きく変わる
教育心理学の調査では、
大学1〜2年の段階で興味が変わる学生は50%以上
というデータがあります。
つまり、
高校の段階で将来のやりたいことを決めるのはそもそも難しい。
だから、「やりたいことが決まってない自分」は全く問題ではありません。
✔ だから“実力で行ける最も上の大学”を狙うのは合理的
理由は3つ:
●① 上位大学ほど進路の自由度が広い
→ 専攻変更・研究・院進・就職の選択肢が豊富。
●② 興味が変わっても対応しやすい
→ カリキュラムや制度が柔軟。
●③ 浪人生は“伸びた科目”がはっきりしている
→ “今年の自分”に合う大学を選びやすい。
●志望理由は小さくていい
「キャンパスが好き」
「通いやすい」
「雰囲気がいい」
これだけで十分。
専門的な志望理由は大学に入ってから育ちます。
5)今日やるべき3ステップ(ここが超大事)
✔ STEP1
第一志望+候補校を3つだけ選ぶ
✔ STEP2
その3校の
配点|方式|共通テスト比率
を1枚にまとめる
(公式リンクからすぐ確認できます)
✔ STEP3
3校を
安心・実力・挑戦(2:2:1)
に分けてみる
足りない枠があれば1〜2校追加する
これで“落ちにくい併願”がほぼ完成します。
まとめ
- 「伸びた科目 × 大学の配点」で相性がわかる
- 併願は「安心2:実力2:挑戦1」で崩れない
- 「やりたいこと」が決まってなくてもOK(興味は後から育つ)
だから今年は
“今の実力で行ける最も良い大学”を目指すのも立派な戦略
■参考リンクまとめ(サイドバー用)
- ▼大学入試センター
受験案内:https://www.dnc.ac.jp/sp/kyotsu/shiken_jouhou/r6_gaiyou.html
実施要項:https://www.dnc.ac.jp/sp/kyotsu/shiken_jouhou/r6_jisshi.html - ▼文部科学省
入学者選抜実施要項:https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/nyushi/1412172.htm - ▼JASSO
奨学金:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/
進学資金シミュレーション:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/koutei/simulation/index.html - ▼e-Stat
学校基本調査:https://www.e-stat.go.jp/statistics/00500202
お問い合わせ
無料体験のご依頼や、受験生活でのご相談、その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください
フォームでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
受付時間 10:00~18:00
(土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く)