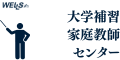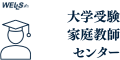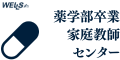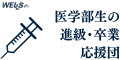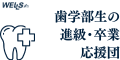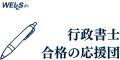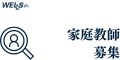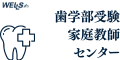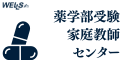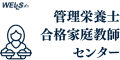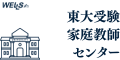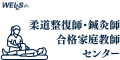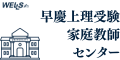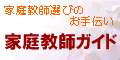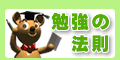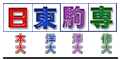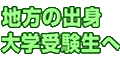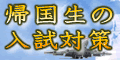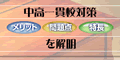模試を「避けずに活かす」低ストレス測定ガイド
はじめに
「実力がついたら受けたい」というお気持ちは、ごく自然なことです。模試は誰かに裁かれる場ではなく、いまの学びを次の一歩につなぐ道しるべ。ここでは、気持ちの負担を増やさずに、穏やかに前進していくためのポイントをまとめました。
1) まずは“動かない日付”をそっと確かめる
共通テストや出願の時期は、毎年公式に決まっています。最初に大学入試センターの受験案内(※受験案内)と実施要項(※実施要項)をご覧になり、試験日や出願期間をカレンダーにそっと置いてみましょう。日にちが見えるだけで、優先順位が落ち着いてきます。
2) 点数だけでなく「時間」もやさしく見守る(低ストレスKPI)
- 成績は得点・偏差値に目がいきがちですが、大問あたりの解答時間も一緒にメモしてみてください。
①知識が足りないのか ②手順で迷ったのか ③時間が足りなかったのか
が分かると、次にやることが無理なく絞れます。 - 日本の公的資料でも、学習の途中での振り返り=形成的評価の活用が大切にされています。模試は「良し悪しの判定」ではなく、次の学びを整える材料として使っていけると安心です(国立教育政策研究所: ※形成的評価資料)。
3) 「受ける → 直す」を48時間で、やさしく1往復
- 復習は48時間以内を目安に、誤答を[知識不足/手順ミス/時間超過]のどれに近いか、短い言葉で分けてみましょう。完璧でなくて大丈夫です。
- 「時間が足りない」が多い時は、次の演習の前に設問ごとの目安時間を先に決めてから解くと、落ち着いて取り組めます。
- 生活面では、睡眠が学習の定着や日中のパフォーマンスに関係します。就寝・起床の時刻をそろえ、朝の光を浴びるところから、ゆっくり整えていきましょう(厚生労働省: ※睡眠ガイド2023 / ※e-ヘルスネット)。
4) 「模試がこわい」気持ちに寄り添う、小さな工夫
- ハードルを下げる:最初は「科目を絞る」「会場より自宅受験から」でもかまいません。目的はいまの位置を知ることです。
- 比べすぎない:結果の他者順位は、すぐには見なくて大丈夫。まずは自分のボトルネック3つだけを拾って、静かに次へつなげましょう。
- スマホと上手に距離を:復習の48時間は学習外アプリに時間制限を。ご家庭で端末分離や時間帯のルールを話し合う際は、最新の実態データが支えになります(こども家庭庁: ※青少年のインターネット利用環境 実態調査 令和6年度/高校生の専用スマホに関する図表PDF:※該当抜粋PDF)。
5) 年 → 月 → 週の「模試カレンダー」例(無理のない最小構成)
- 年:共通テストや出願などの固定日を、いちばん先に置きます(※受験案内 / ※実施要項)。
- 月:その月は模試 → 復習 → 面談(15分でも十分)を固定ブロックとして確保。
- 週:模試がない週は、タイムトライアル(15/30/60分)×3本で“時間の感覚”をやさしく保ちます。
※就寝・起床の固定は学びの土台です。無理のない範囲で、少しずつ(※e-ヘルスネット)。
6) つまずきが出たときの言い換え
- 落ち込んだ → 「原因を3つ見つけられた。次の一歩が見えた」
- 復習が重い → 「各大問で“次回やること”を1つだけ書けば十分」
- 予定が崩れた → 「固定日だけ守れたらOK。細かい調整は来週に」
参考(※参照名|日本の公的情報のみ)
- 大学入試センター|※受験案内
- 大学入試センター|※実施要項
- 厚生労働省|※睡眠ガイド2023
- 厚生労働省|※e-ヘルスネット
- こども家庭庁|※青少年のインターネット利用環境 実態調査 令和6年度
- 国立教育政策研究所|※形成的評価資料